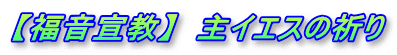
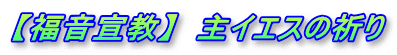
「さて、イエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて、淋しい所へ出ていき、そこで祈っておられた」(マルコ1:35)
3月に入りました。 3-4月は教会行事も多く重なり、特にイースターに向けて
教会もこれから忙しい時期を迎えようとしています。しかしながら、イエス様の1日のはとてもくらべものになりません。イエス様は朝から夜まで
超多忙な日々でした。
1. イエス様の安息日
イエス様は弟子たちと共に
ユダヤ人の戒めに従い、安息日の朝にユダヤ教会堂に行き 、神の国の福音を会衆に語り、悪霊に支配された人から悪霊を追い出し、午後からはペテロの姑の家で彼女の熱病を癒されました。小さな村ですから噂はたちまち広がり、安息日が終わる夕刻には、ペテロの姑の家の周囲を、病で苦しむ人々が癒しを求めて大勢押しかけ取り巻きました。通りにまで溢れていたようです。安息日には医療行為をすることが禁じられていたので、安息日があける夕方から、人々が一斉に押しかけてきたのです
。それはまるで 連休明けに病院に人が殺到し混雑する光景とよく似ています。イエス様は彼らを癒し、また悪霊を追い出し、救いを求める声に応えられました。ペテロの姑が用意した食事をまともに食べることができたかもあやしいものです。寝食を忘れて治療にあたる「赤ひげ先生」のような多忙さだとイメージできます。
イエス様は朝早く起きて一人で祈っておられました。
弟子たちはイエス様に助けを求める人々にあたかも叩き起こされたかのように目覚め、「イエス様はどこへ行ったのだ」と、慌てて探し回ったようです。イエス様の祈りから3つ 学びましょう。
1) イエス様は祈っておられた(35)。ここに記されている動詞は、未完了形が使用されていますからいつものように祈り続けておられたことを意味します。弟子たちはまだイエス様の祈りの習慣を理解していませんでした。イギリスの聖書学者バークレーは「繁栄の日々に神に届けられる
祈りは一つであるが、困難な時には一万の祈りがなされる」あるいは「人生の晴天の日には決して祈らなかった人が、冷たい風が吹いてきた時には祈り始めるのである」とイギリスの格言を引用しています。多くの人々が困難に陥った時、または人生が痛手を与えた時にだけ神を思い出し始めるのであるとも記しています。日本でも困った時の神頼みと言いますが、ご利益的信仰はどこの国でも同じようです。バークレーは「神は不幸な日にだけ利用されるお方ではなく
私たちの日々の生活の中で 毎日、
愛され 覚えられ、語り合われるべきお方である」と、勧めています。祈りは「1年365日の神様との語り合い」です。私たちの父なる神との面会日は特別の日にだけ許可されているのでなく、毎日、用意されているのです。
2) イエス様にとって
朝の祈りの時は霊的な力の泉でした
イエス様の宣教はこの世を支配しているサタンとの霊的な戦いの日々でした。イエス様の宣教のことば、「神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じよ」(1:5)は、生涯にわたって語りつづけられました。神の国とは、神のご支配を意味します。
暗闇の支配者であるサタンと悪霊にとってキリストの宣教とともに 神の御国の支配が新しく始まったことは脅威でした。恐れおののき激しく抵抗しています。それゆえにイエス様の宣教は霊的な戦いであり、そのためには
父なる神様から日々、力と愛が供給されることが必要でした。このため、イエス様は一人で常に祈られたのです。
「隠れたところで祈りなさい」(マタイ6:6)と言われた イエス様は、ご自身が何よりも密室での祈りの時を大切にしておられ、弟子たちに範を示されたのでした。
砂漠の小さな昆虫たちのドキュメントを見たことがあります。コガネムシやテントウムシやフンコロガシなどの生物が、全く水がない世界で
どうして生き延びているのか不思議に思っていましたが納得できました。朝、太陽が昇る前に
彼らは土から出てきて、砂の上でじっと待ちます。すると、甲羅の上に空気中の水分が小さな水滴となって溜まってきます。じっと待ち続け、ある量になったら、後ろ足を立てて、逆立ちする姿勢をとるのです。そうすると、背中の甲羅から口元に水滴が流れ込んでくる。その水滴を一日のいのちの糧として生きているというのです。私たちも忙しければ
忙しいほど 祈りの時が必要です。
朝、早く祈りの時を持てる人もいれば、
朝は台所が戦場と化して、朝食づくりにお弁当作り。子供と主人を叩き起こして、学校と会社に送り出し、その後は掃除洗濯。それからデボーションタイムを持つ方もおられます。仕事帰りの喫茶店で1時間、信仰書を開いて恵みをいただく人もおられます。工夫さえすれば、時間に束縛されず、いつでもどこでも神様との交わりの時は持つことができます。神様との御言葉による交わりの時、御霊による満たしの時、
静かに自らを顧みる時を持つことによって、霊的な恵みの補強と補給を受けることができます。疲れた魂もリフレッシュされ、いつしかこの世的な価値観や主義主張、世の流行に流されがちな考え方を聖書の真理へとアップデートする時が私たちには必要です。御言葉のシャワーを浴びて、この世の塵、芥とほこりを洗い流すことも必要かもしれません。観月橋のたもとにある世光教会の榎本先生は、アシュラムという祈りの運動を全国的に広げ、祈りの指導をされた神の素晴らしい器でした。先生は「
朝の15分があなたを変える、あなたの生活を変える、あなたの人生を変える」と語り続けました。祈りは霊の泉です。祈りのある所に、いのちの水は湧き上がります。
3) イエス様は
執り成しの祈りをささげました
イエス様は人里離れたところで祈られました。父なる神様との個人的な交わりの時を常に大切にもたれましたが、同時に、イエス様の祈りは、病気で苦しむカペナウムの町の人々のため、悪霊に支配され人間としても尊厳や価値を奪われてしまい不安と混乱の中に投げこまれている人々のため、そしてこれから十字架を負うて幾多の困難を越えていくことになる弟子たちのために、隠れたところで、執り成しの祈りをされておられたことも忘れてはなりません。
イエス様の祈りは「天で御心がなるごとく地にもなりますように」(マタイ6:10) との言葉の中に、すべてが凝縮されていると私は思います。「地においても御心がなる」、このことこそが神の国・神の御支配そのものだからです。この目的のためにわたしたちは召されたのです。私たちは御国の祭司(1ペテロ2:9)とされました。大祭司であるイエス様のもとで仕えるために地上に遣わされ「執り成しの祈り手」とされた、御国の祭司なのです。
3. さあみんなで出かけよう(38節)
ペテロ
たちはイエス様が家におられないと知って、後を追ってやってきました。「みんながあなたを探し求めています。こんな場所でこんなことをしていても時間の無駄ではないでしょうか」とばかりに、連れ戻しに来たのです。しかし
イエス様はカペナウムの町には戻りませんでした。「さあ行こう」(出かけよう)と イエス様は弟子たちを促して、ガリラヤ全地域の町々、村々を巡り歩き、神の御国の福音を宣べ伝えたのでした。
イエス様の宣教は、神の国の福音を宣べ伝えることを第一としつつ、病を癒し、悪霊に支配された人々に解放と自由をもたらしました。宣教
癒し 奉仕
これらはイエス様にあって一つに溶け合っていました。分けることはできませんが、イエス様は福音を宣べ伝えることを第一とされました。癒しや悪霊の追放といった奇跡を第一とされるようなところからは、イエス様は去って行かれます。教会が学ぶべき第一の働きは、神の国の福音の宣教であり、福音の恵み、すなわち神の国の平和と義と愛に一人一人が生きていくことなのです。
御国の祭司とされた私たちですから、良き祈り手であり、天上の大祭司なるイエス様からさらに深く、多くを、学ばせていただきましょう。
宣教の方策よりは、弟子たちはイエス様から「祈ること」を学んだのです。